■ はじめに
「うちはウナギを食べないんだ」
「うちではキュウリは作っちゃいけないのよ」
そんな言葉を聞いたら、多くの人は驚くかもしれません。
ですが日本の農村部には、今もこうした**“食にまつわる家の掟”**が静かに受け継がれている家があります。
我が家もそのひとつ。
代々「ウナギを食べてはいけない」と言われ育ちました。そして西日本には、同じように「キュウリを作ってはいけない」家があるというのです。
一体なぜなのでしょう?
今回はその背景にある民間信仰と地域のしきたりを探ってみます。
■ ウナギは蛇の化身?虚空蔵信仰と“食べない理由”
私の家系でウナギが禁止されている理由は、「虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)」の信仰にあります。
虚空蔵菩薩とは、知恵や記憶の仏さま。
とくに東北・関東の一部地域では、この菩薩が蛇を眷属(けんぞく=使い)とするという信仰があり、蛇に似たウナギを食べることがタブーとされてきたのです。
-
長くぬるぬるとした体
-
水陸両方で生きる神秘的な性質
-
収穫期の水辺に現れる様子
これらの特徴が「蛇」に重ねられ、「神の使いを食べるなどもってのほか」とされたのです。

■ 「そういう家だから」――しきたりとしての継承
子どものころ、ウナギを食べてみたいと思ったこともあります。
でも家族はこう言いました。
「うちはそういう家だから」
理由は深く語られないまま、掟としてただそこにある。
でも、祖父母や親たちが無意識のうちに守ってきたことには、目に見えない敬意や祈りが宿っているように思えてなりません。
■ 西日本に伝わる“キュウリを作ってはいけない”理由
そしてもうひとつ、私が驚いたのは「キュウリを作ってはいけない家がある」という西日本の信仰です。
これは主に、京都の**八坂神社(祇園信仰)**に由来するとされます。
この神社の神紋である「木瓜紋(もっこうもん)」――
これが、キュウリの輪切りの断面と酷似しているのです。
🥒 キュウリを輪切りにすると → ご神紋に見える
→ 神の印を食べることになる → 不敬だ!
そのため、京都や滋賀、奈良、大阪の一部地域では、次のような家の掟が今も残っています。
-
キュウリを栽培しない
-
食べる時は輪切りを避ける
-
祇園祭の期間中は絶対に食べない
■ キュウリとウナギ、そして“作らない/食べない”ことの意味
ウナギを食べない
キュウリを作らない
それは「科学的な理由」でも「栄養学的な問題」でもありません。
“敬うべきものを口にしない”という、祈りに近い感覚が、家の中で受け継がれてきたのです。
食べるものの選択にすら、家族の記憶や地域の信仰が宿っている。
それは“しがらみ”ではなく、文化としての重みなのかもしれません。
■ おわりに:伝統とは「よくわからないけど、続いているもの」
今の時代、ウナギもキュウリも年中どこでも手に入ります。
でも、我が家ではどんなに食卓が華やかになっても、ウナギの蒲焼は出てきません。
同じように、西日本のある家では、夏の定番であるキュウリすら、育てることが許されない。
それを「非合理」と笑うこともできます。
でも私は思います。
「そういう家だから」という一言の中に、
何世代もの“語られない物語”が詰まっている、と。
📚 参考文献・出典
-
山折哲雄『日本人の宗教心』(岩波新書)
-
宮田登『民俗宗教論』(講談社学術文庫)
-
石井正己 編『暮らしのなかの民間信仰』(吉川弘文館)
-
村上重良『日本の宗教』(中央公論社)

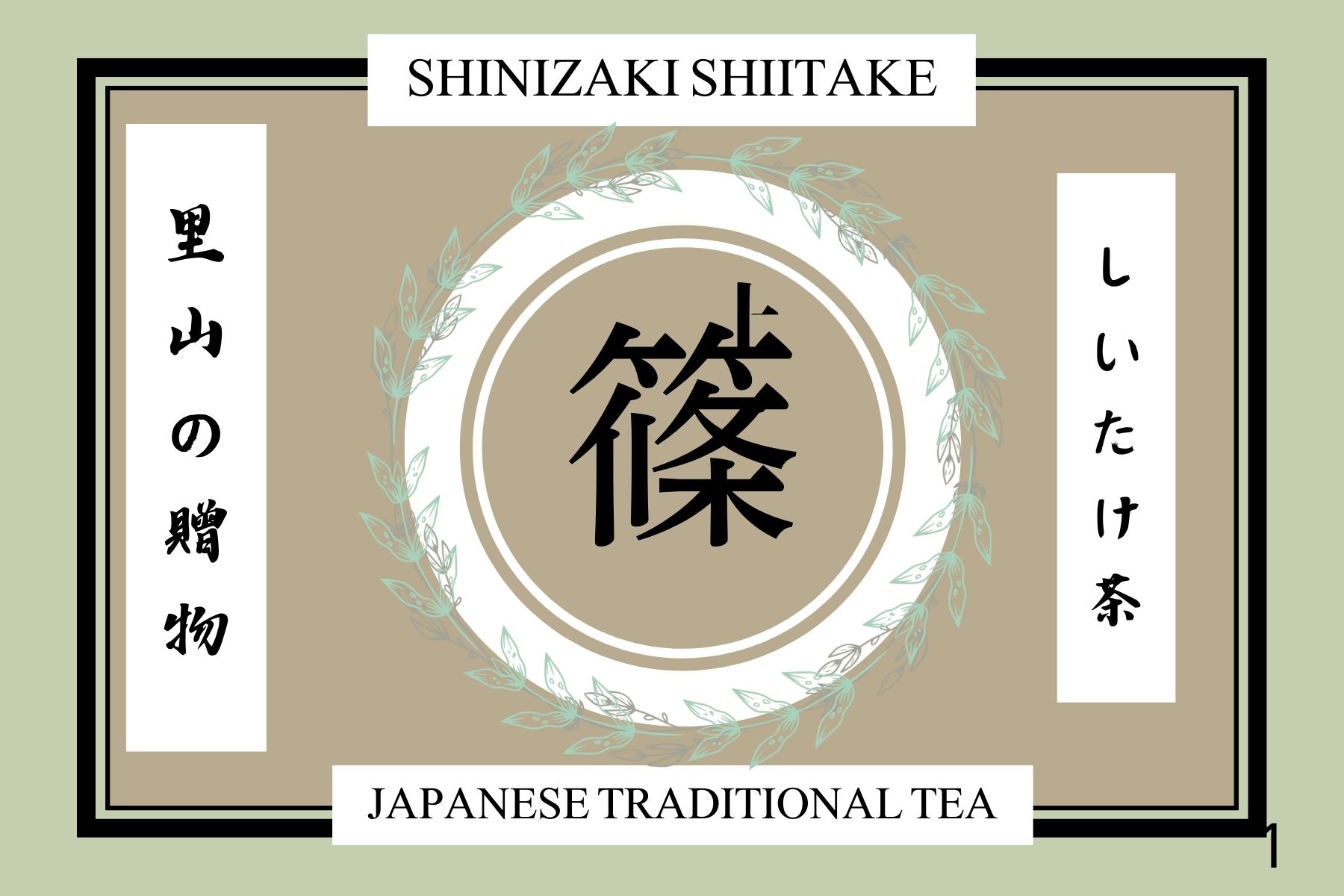
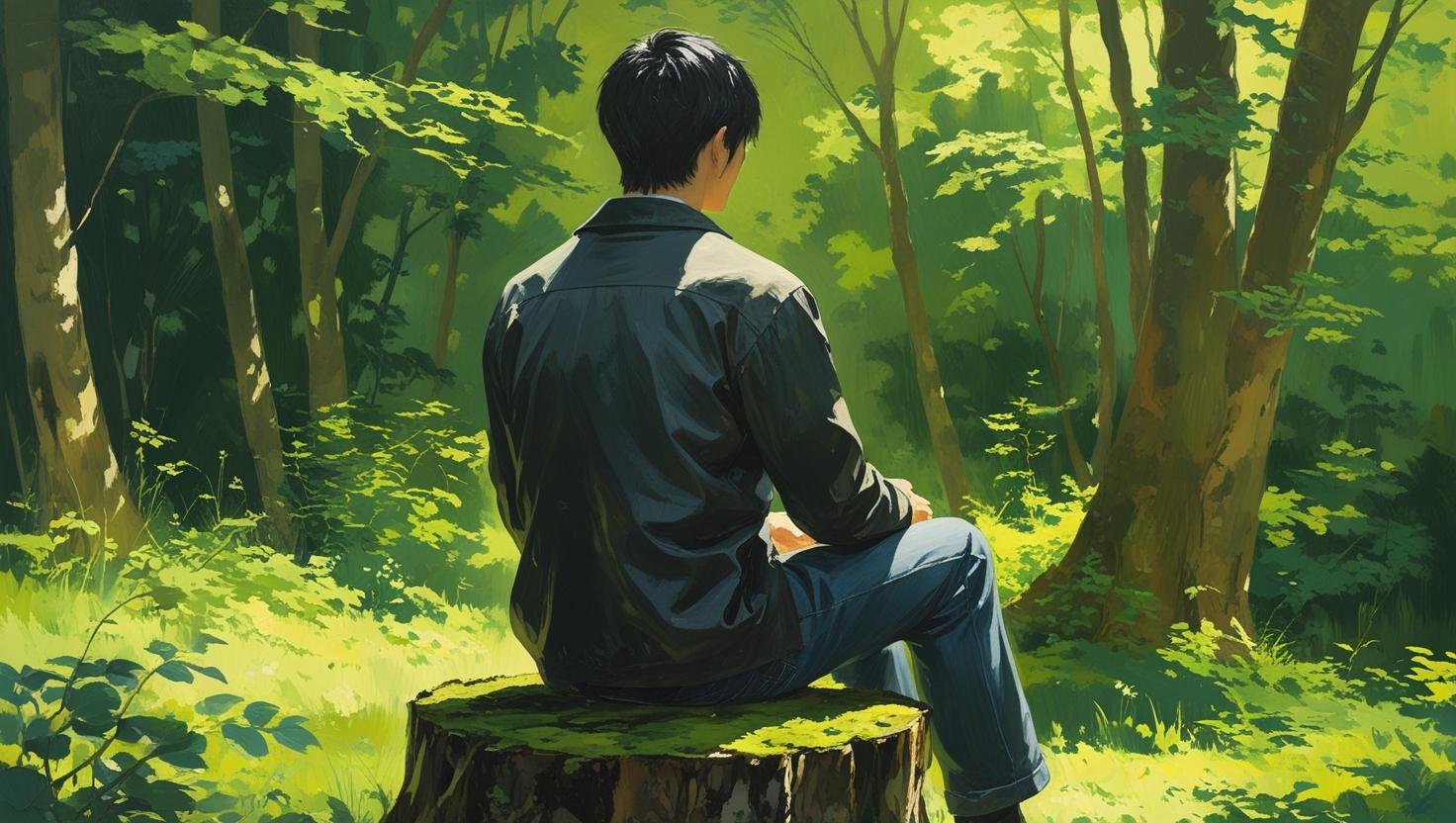
コメント