なぜトリュフは昔は豊作、今は希少?
世界三大食材として有名な「トリュフ」。高級フレンチやイタリアンでは欠かせない、あの香り高い食材も、実は「きのこ」なんです。
トリュフが幻の食材と呼ばれる理由を解説。菌根菌との共生、農業近代化、白色腐朽菌の進化まで、専門農家がわかりやすく説明します。
でも、シイタケやマツタケとはちょっと違います。
トリュフは「担子菌」という傘を作るきのこではなく、「子嚢菌(しのうきん)」という袋状の胞子を作る菌類に分類されます。
土の中で木の根と「菌根(きんこん)」を作り、栄養を融通し合う共生関係を築いて育つ——。
それこそが、トリュフというきのこの最大の秘密です。
トリュフは菌根菌の仲間
トリュフはハシバミやオーク、ブナなどの樹木の根と共生する「菌根菌」です。
菌根菌は、木の根とつながって栄養や水分を交換し合います。
木は光合成で得た糖をトリュフ菌に渡し、トリュフ菌は土壌中の水やリン酸を木に供給します。
その共生の結果、トリュフ菌糸は木の根の周りに広がり、「コロニー」を形成します。
周囲の草を抑制してできる「ブリュレ(Brûlé、焼け地帯)」はトリュフ畑の目印でもあります。
かつては豊作だった時代
フランスでは1940年代頃まで、黒トリュフが年間1000トン近く収穫されていたといいます。
伝統的な農法では、自然林や牧草地をうまく維持し、菌根菌との共生を守っていました。
農業の近代化がもたらしたもの
しかし、1950年代以降の農業の近代化で状況は変わりました。
- 土壌の深耕による根の切断
- 化学肥料や除草剤の普及
- 牧草地や雑木林の開墾
これらが、トリュフ菌と木の根の「菌根」を破壊し、コロニーを維持できなくなりました。
激減した収穫量と高級食材化
こうした変化によって、フランスなどのトリュフ収量は1960年代から急激に減少し、1990年代には数十トン規模にまで落ち込みました。
「幻の食材」「超高級食材」と呼ばれるようになったのは、こうした背景があります。
今も続く挑戦
現在では、人工的に接種した苗木を植える「トリュフ林」の整備が進められています。
フランス、イタリア、スペインなどで、菌根菌との共生を再び取り戻すための努力が続いています。
豚や犬がトリュフを探す理由
伝統的にトリュフを探すには「雌豚」が使われてきました。
なぜかというと、トリュフの香りには「アンドロステノン」という成分が含まれており、これは豚の雄の性フェロモンとよく似た化学構造をしています。
そのため、雌豚はこの匂いに非常に敏感で、まるで性的な魅力を感じるかのようにトリュフを夢中で掘り当てるのです。
しかし豚には大きな問題も
- 見つけたトリュフをその場で食べてしまう
- 力が強く、奪い返すのが大変
- 輸送や管理が面倒

こうした理由から、豚は次第に使われなくなっていきました。
そこで「犬」が主役に
現在は犬がトリュフハンターの相棒として主流です。

訓練がしやすい
「掘ったら渡す」という指示を理解する
人間に協力的で制御しやすい
特にテリア系やラブラドールなど、嗅覚が鋭くて従順な犬種が選ばれています。
豆知識
フランス語では「トリュフを探す犬」をChien truffier(シアン・トリュフィエ)と呼びます。
イタリアのピエモンテ州などでは、犬を育てて訓練する「トリュフ犬学校」も存在します。
トリュフ犬は血統を管理され、親から子へ「探す才能」が受け継がれるのです。
まとめ
✔️ トリュフはハシバミやオークなどと菌根を作って共生する「菌根菌」。
✔️ かつては豊作だったが、農業の機械化や除草剤の使用などで菌根が破壊された。
✔️ 1990年代には収量が激減し、今では希少な高級食材に。
✔️ 伝統的に豚が使われたのはフェロモンの匂いに反応するからだが、現在は犬がパートナーとして活躍中。
トリュフは自然の神秘そのもの。
その成長には木と菌根菌の見えない助け合いが必要であり、それを探し出すために人と動物が協力してきた歴史があります。
一つの食材の裏に、これだけの自然と人間の物語があるということを、ぜひ味わってみてください。
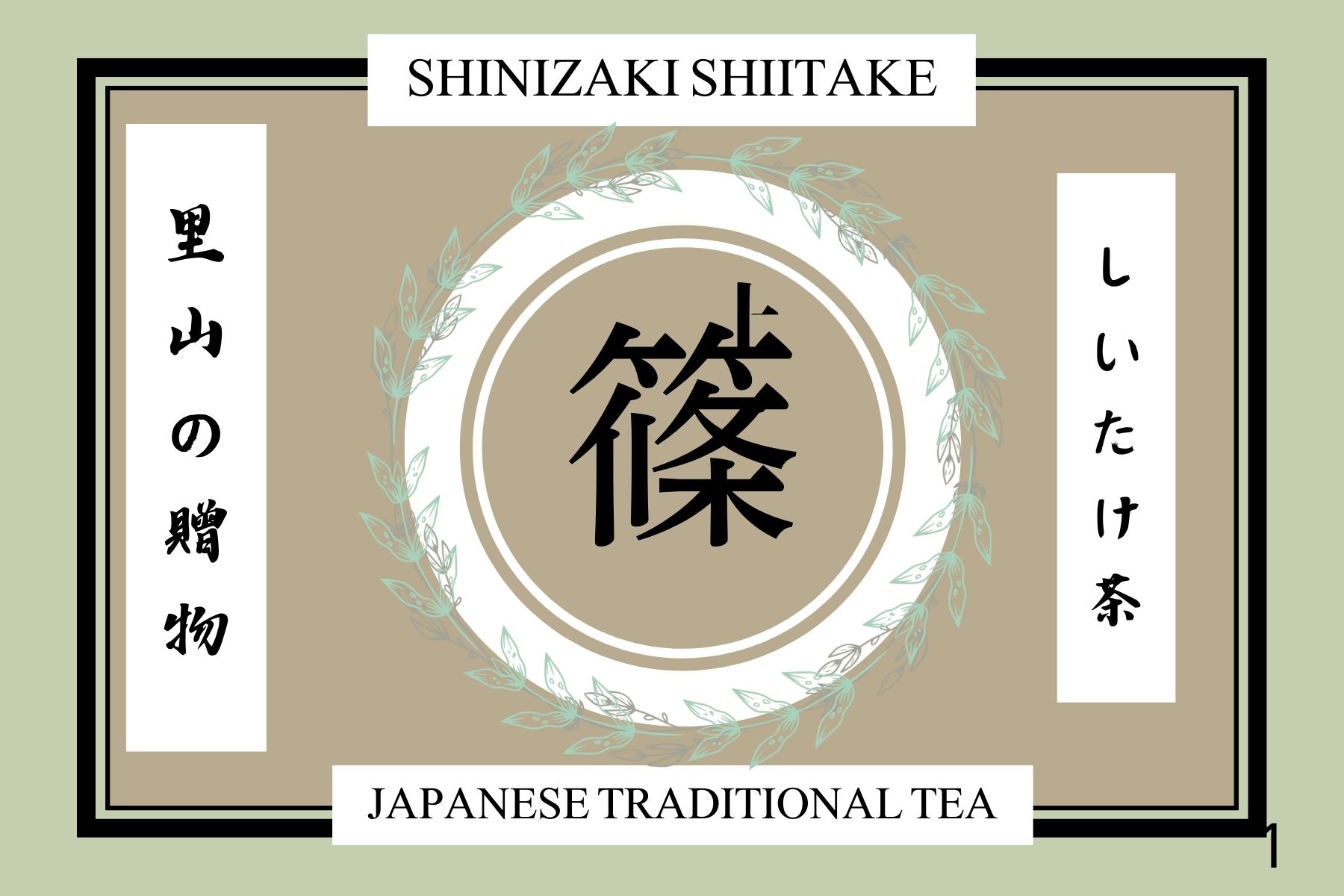

コメント