しいたけ茶を飲みながら考えた、農業従事者の平均年齢が70歳を超える本当の理由とは?定年後に始める趣味農業や“土地を守るためだけ”の耕作が統計を歪めている現実を、農業委員を3期務めるわたくしが現場目線で語ります。
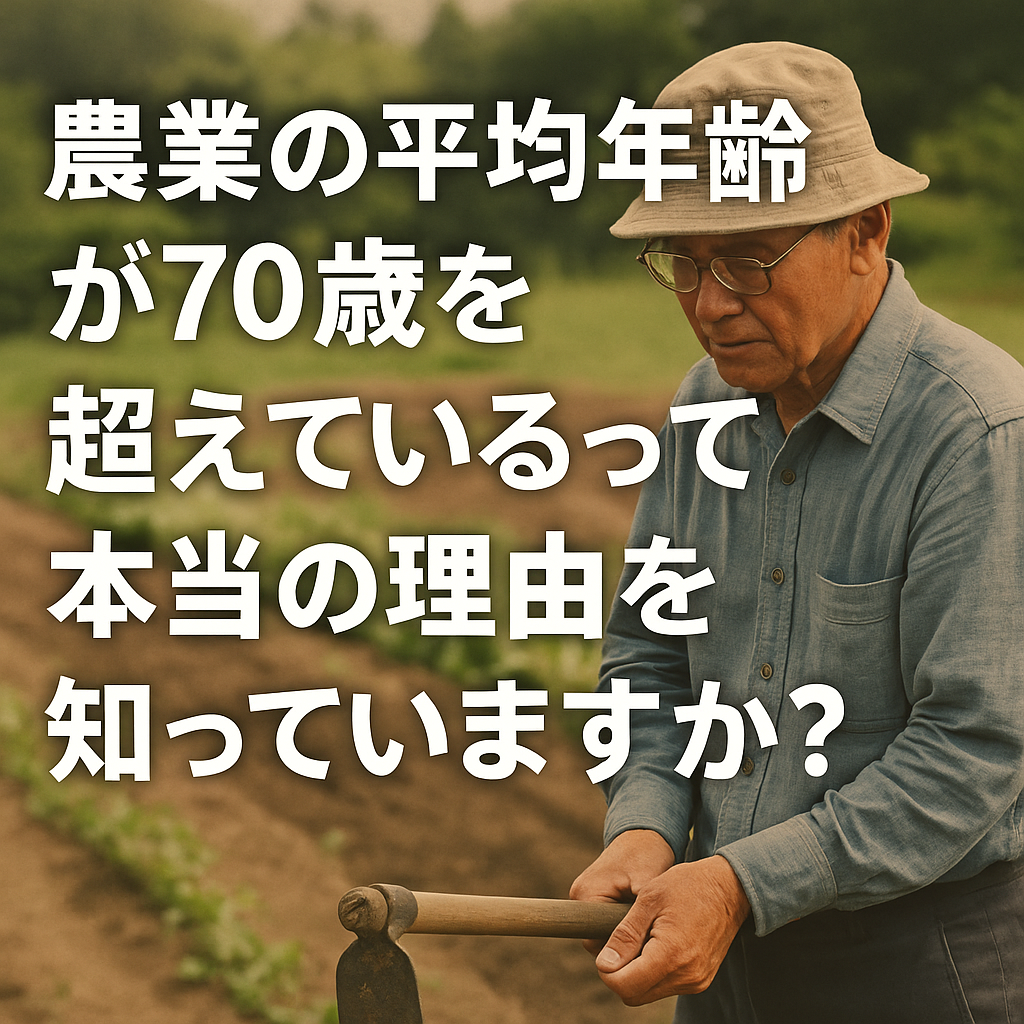
はじめに:
「農業者の平均年齢は70歳を超えました」――
テレビや新聞がよくこんな風に報じますが、その言葉に違和感を覚えたことはありませんか?
現場で鍬(くわ)を持ち、土にまみれている私からすれば、
「それ、本当に“農家”の話ですか?」
と突っ込みたくなるのです。
1. 平均年齢70歳超えの正体
なぜそんなに高齢なのか?
理由はいたって単純。
農業で食っていこうとする人はごくわずかで、多くは「定年後のゆる農業」だからです。
- 会社勤めを終え、年金の足しにと畑を耕す
- 親の土地を荒らしたくないから草刈りついでに野菜を植える
- 月1回、直売所にちょっとだけ持っていく
そんな人も「販売農家」「農業従事者」に含まれます。
2. 統計の“ごまかし”に近い定義
農林水産省の定義では、
「年間15万円以上の売上」=販売農家
「年間60日以上作業すれば」=基幹的農業従事者
となるため、「趣味で畑に出てるだけ」の人もプロと同じように数えられてしまいます。
これじゃあ、「同じ農家として扱うな」と言いたくなるのも当然です。
3. 土地を守るという呪縛
農業が儲からない。
でも、先祖代々の田んぼや畑を荒らすのは忍びない。
だから耕す。配る。売れなくても作る。
これは、農業というより“供養”や“責任”のようなものです。
日本では「農地を荒らすな」「ご先祖に顔向けできない」という強いプレッシャーがあります。
4. 世界でも似たような現象はあるが…
ドイツにも週末農園、韓国にも高齢の自給農家はあります。
しかし、ここまで農地を神聖視し、転用も売却も難しく、相続がややこしい国は日本だけです。
結果、「辞められない農業」が平均年齢を押し上げています。
🌾 他国との違いをざっくり比較すると:
| 項目 | 日本 | アメリカ | ドイツ | フランス | 韓国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農家の定義 | あいまいで広すぎ | 生産量と利益で定義 | 明確に区別 | 法人化が進む | 小規模自給が主流 |
| 土地の神聖性 | 高い(先祖・墓とセット) | 低い(資産の一部) | 中程度 | 土地と文化が結びつく | 日本と似ている |
| 農地転用 | 難しい | 比較的自由 | やや制限 | 中程度 | 制限あり |
| 耕作放棄地の多さ | 非常に多い | 少ない | 少ない | 少ない | 多いが回復中 |
5. 農政の問題は“ひとくくり”にすること
スーツを着て畑を歩いたこともない人が、
「スマート農業で若者の参入を」
「高齢化が問題」
と語るのを見るたびに思います。
“農業で稼ごうとする人”と“土地を守る人”は別物なのです。
それを同じ「農家」とひとくくりにするから、おかしな統計と政策が生まれる。
おわりに:
農業の平均年齢が70歳を超えた。
それは「高齢化の危機」ではなく、
「農業を諦めきれない人たちの静かな抵抗」
なのかもしれません。
現場の声が聞こえない政策より、
現場にいる私たちの“つぶやき”のほうが、ずっとリアルで未来へのヒントになると思っています。
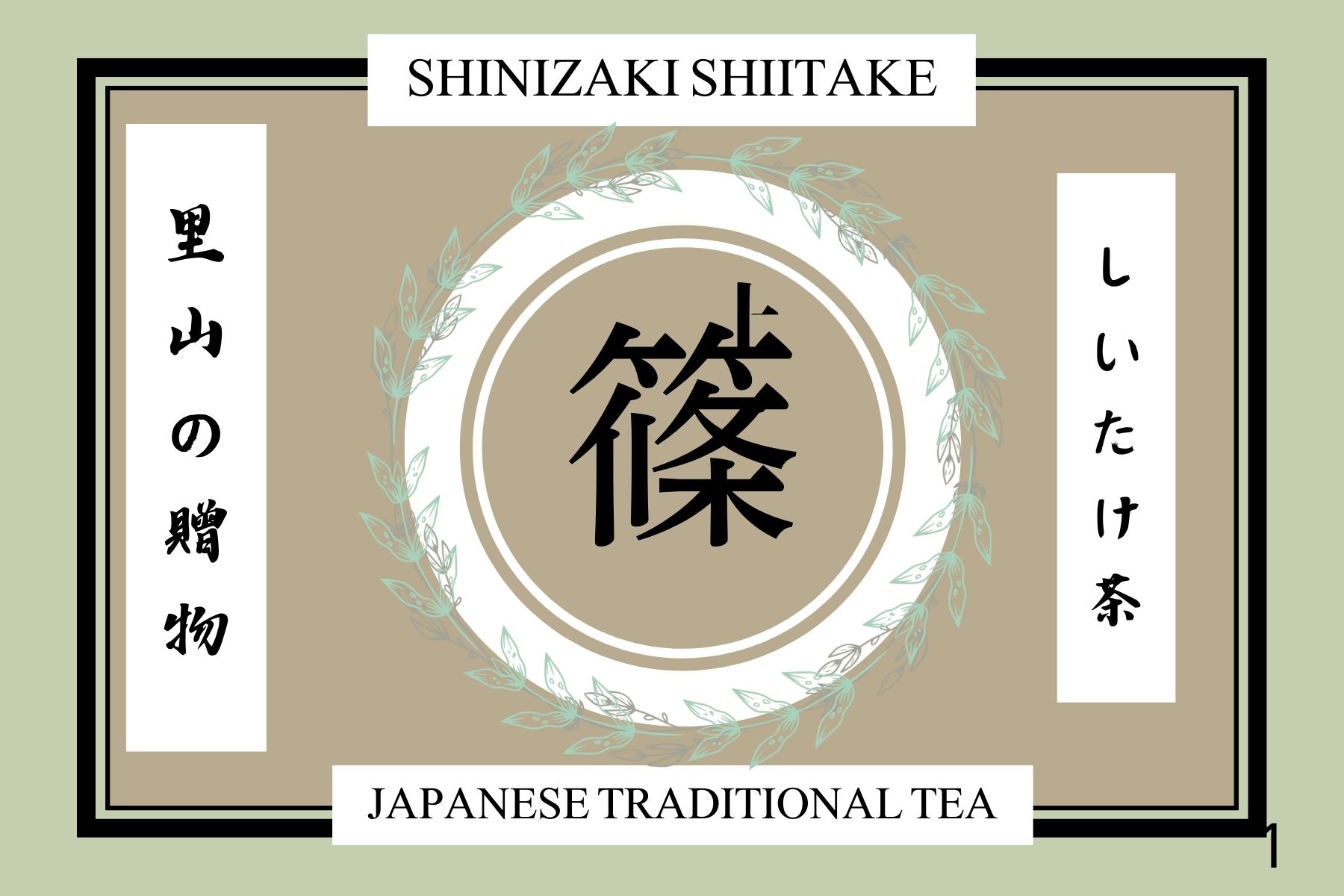
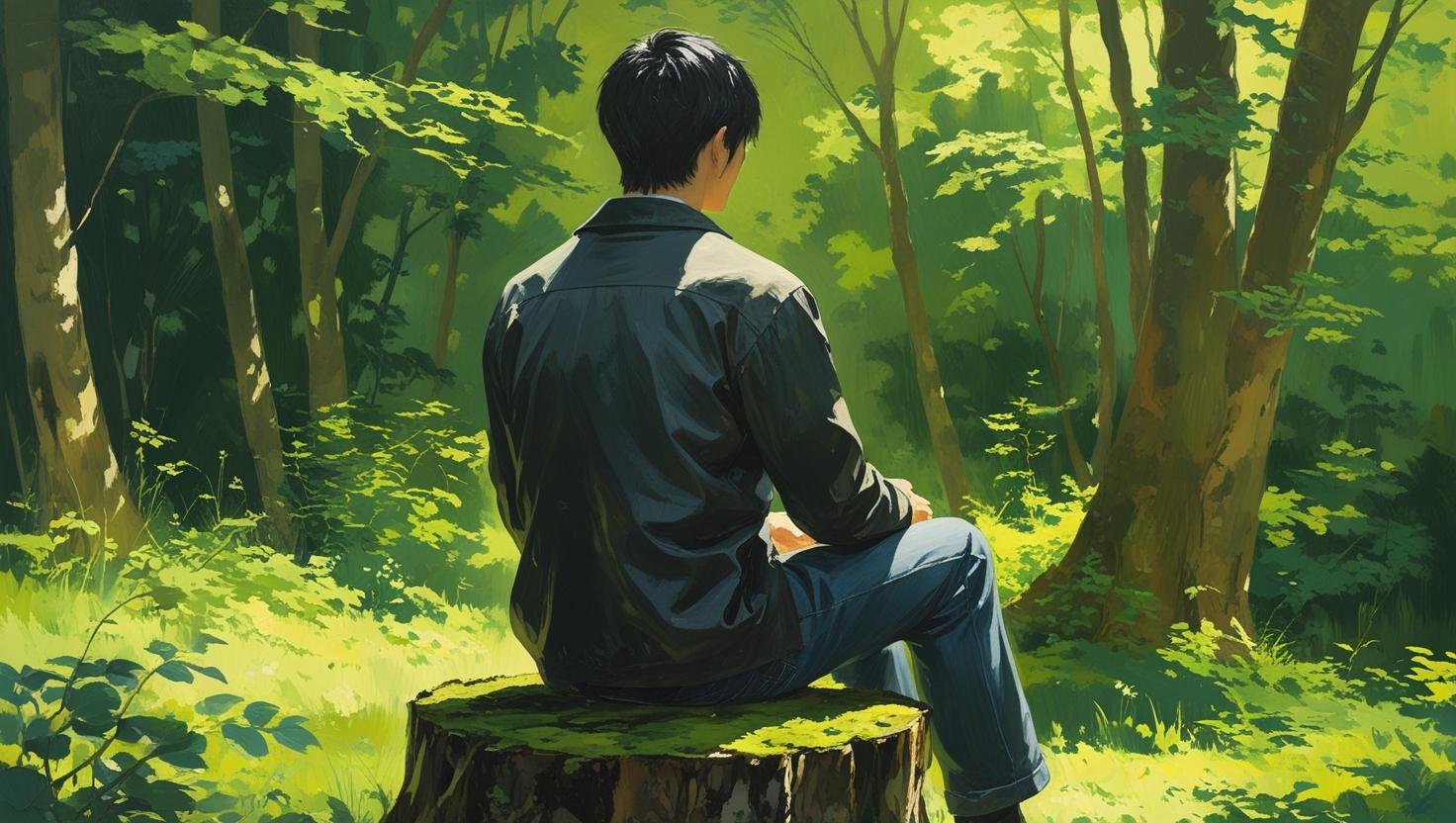
コメント